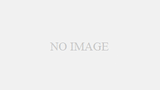家庭菜園でセロリ栽培に挑戦したいけれど、収穫時期がいつなのか気になりますよね。セロリの栽培は難しいというイメージがあるかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば大丈夫です。
この記事では、春からの種まき時期や基本的な育て方はもちろん、収穫量を増やすわき芽の処理、品質を高める栽培における遮光のコツ、具体的な収穫方法まで詳しく解説します。
さらに、植えっぱなしでの冬越しは可能なのか、といった疑問にもお答えし、初心者の方が失敗しないための情報を網羅しました。
セロリの収穫時期はいつ?栽培計画の基本

- セロリの自家栽培は本当に難しい?
- セロリの種まき時期と育て始めのコツ
- 春から始めるセロリ栽培のポイント
- プランターでのセロリの育て方
- 露地でのセロリ栽培を成功させるには
セロリの自家栽培は本当に難しい?

結論から言うと、セロリの自家栽培は他の夏野菜に比べると少し手間がかかるため、難易度はやや高めと言えます。しかし、栽培のポイントさえしっかり押さえれば、初心者の方でも美味しいセロリを収穫することは十分に可能です。
セロリ栽培が難しいと言われる主な理由は、その栽培期間の長さにあります。種まきから収穫まで約150日、つまり4ヶ月以上かかることも珍しくありません。
この長い期間、セロリの生育適温である15~20℃を維持しつつ、適切な水分と肥料を供給し続けるという、きめ細やかな管理が求められます。特に、セロリは元々冷涼な気候を好む野菜であるため、高温多湿となる日本の夏をいかに乗り切るかが栽培における最大の課題となります。
また、生育期間が長いということは、それだけ肥料切れを起こしやすかったり、病害虫に遭遇するリスクが高まったりすることも意味します。
これらの複合的な要因が、「セロリは難しい」というイメージにつながっているのです。ただ、これから解説する対策を一つひとつ丁寧に行えば、これらの課題は十分に克服できます。
セロリ栽培成功の4大ポイント
- 苗の購入から始める:育苗だけで2ヶ月以上かかるため、初心者は khỏe mạnhな市販の苗から始めると、栽培のハードルがぐっと下がります。
- 土作りを丁寧に行う:セロリは酸性土壌では根の伸長が妨げられ、養分をうまく吸収できません。植え付け前に土壌の酸度調整をしっかり行いましょう。
- 夏場の管理を徹底する:直射日光を避けるための遮光や、地温の上昇と乾燥を防ぐ敷きわらは、夏越しに不可欠な対策です。
- 追肥を忘れない:栽培期間が長いため、元肥だけでは栄養が不足します。定期的な追肥で、生育を最後までサポートします。
このように、いくつかの重要なポイントを理解し、適切なタイミングで実践すれば、自家栽培は決して不可能な挑戦ではありません。この記事で解説する手順に沿って、ぜひ美味しいセロリの収穫にチャレンジしてみてください。
セロリの種まき時期と育て始めのコツ

セロリを種から育てる場合、種まき時期は収穫成功を左右する非常に重要な要素です。セロリの発芽や生育に適した温度(15~20℃)を考慮し、お住まいの地域の気候に合わせて最適なタイミングで作業を始めましょう。
セロリの栽培カレンダー(地域別)
地域ごとの栽培スケジュールの目安は以下の通りです。品種によっても時期が多少異なるため、種袋の裏面も必ず確認してください。
| 地域 | 種まき | 植え付け | 収穫 |
|---|---|---|---|
| 寒冷地 | 4月~5月 | 6月~7月 | 9月~11月 |
| 中間地 | 5月~7月 | 7月~9月 | 10月~1月 |
| 暖地 | 8月~9月 | 10月~11月 | 1月~4月 |
発芽の重要ポイント:光と水
セロリの種は「好光性種子(こうこうせいしゅし)」と呼ばれるタイプで、発芽するために光を必要とします。そのため、種をまいた後に土を厚くかぶせすぎると、光が届かず発芽率が著しく低下します。土は種が隠れる程度にごく薄くかけるのが鉄則です。
また、発芽まで10日~2週間ほどかかるため、その間は絶対に土を乾燥させないよう、霧吹きなどでこまめに湿り気を与えましょう。
育て始めのコツ:育苗管理
セロリの種は発芽が揃いにくいため、畑やプランターへの直播きよりも、育苗ポットやセルトレイで苗を育てる「移植栽培」が圧倒的におすすめです。温度や水分を管理しやすい環境で、確実にある程度の大きさまで育ててから植え付けることで、初期の失敗を防げます。
種は一晩水につけて吸水させてからまくと、発芽が促進されます。本葉が2~3枚になったら元気の良いものを残して間引き、本葉が7~8枚になるまで、約2ヶ月半~3ヶ月ほどじっくり育苗します。この育苗期間の長さが、セロリ栽培の大きな特徴です。
育苗期間は長いですが、ここでしっかりとした苗を作ることが、その後の生育を大きく左右します。焦らずじっくり育てましょう!
春から始めるセロリ栽培のポイント

春に種まきをして栽培を始める場合、生育期間が真夏と重なるため、高温対策が最も重要なポイントになります。セロリは本来、ヨーロッパなどの冷涼な気候が原産の野菜なので、日本の厳しい夏を乗り切るための工夫が収穫の成否を分けます。
最重要課題:土作りと植え付け
まず、苗を植え付ける2週間以上前に、畑に苦土石灰を1㎡あたり約100g~150gまいてよく耕し、土壌の酸度をpH6.0~6.5の中性に近い状態に調整しておきましょう。
日本の土壌は雨が多いため酸性に傾きがちです。農林水産省も土づくりの重要性を説いていますが、セロリは特に酸性土壌を極端に嫌うため、この作業は絶対に省略できません。
植え付け1週間前になったら、完熟堆肥を1㎡あたり2~3kg、化成肥料を100gほど施し、水はけと水持ちの良い、栄養豊富な土壌を作ります。
苗の植え付けは、本葉が7~8枚に育った頃が適期です。根鉢を崩さないようにポットからそっと取り出し、深植えにならないよう、株元が少し見える程度に浅めに植え付けるのがコツです。
夏を乗り切るための具体的な管理術
気温が25℃を超える日が続くようになったら、本格的な夏越し対策を始めます。具体的な対策は以下の通りです。
夏越し3点セット
- 遮光:遮光率50%程度の黒またはシルバーの寒冷紗(かんれいしゃ)をトンネル状に張り、強すぎる直射日光を和らげ、株の消耗を防ぎます。
- マルチング(敷きわら):株元に稲わらや刈草、腐葉土などを5cmほどの厚さで敷くことで、土の急激な乾燥を防ぎ、地温の上昇を効果的に抑えることができます。
- 水やり:夏場は土が乾きやすいため、特にプランター栽培では水切れに要注意です。気温が上がる前の早朝や、涼しくなった夕方に、株元にたっぷりと水やりをします。
人間も夏バテするように、セロリにとっても夏は過酷な季節です。少しでも涼しい環境を作って、夏越しをサポートしてあげましょう!
プランターでのセロリの育て方

セロリは、庭や畑がない場合でもプランターを使えばベランダなどの省スペースで手軽に栽培できます。
プランター栽培は、台風の時などに移動させて被害を避けたり、日当たりを調整したりできる管理のしやすさが大きなメリットです。
プランターと用土の選び方
プランターは、セロリの根がしっかりと張れるように、深さが30cm以上ある深型のものを選びましょう。容量としては20リットル以上が目安です。
標準的な幅60cmのプランターであれば、2株から3株程度を育てることができます。用土は、肥料分などが予め調整されている市販の野菜用培養土を使うのが最も手軽で確実です。
自分で配合する場合は、赤玉土(小粒)6:腐葉土3:バーミキュライト1の割合で混ぜ、緩効性化成肥料を少量加えます。プランターの底には、水はけを良くするために鉢底石を2~3cm敷き詰めるのを忘れないようにしましょう。
植え付けと日々の管理のコツ
植え付け方は露地栽培と同様に、根鉢を崩さずに浅めに植え付けます。プランターは露地栽培に比べて土が乾燥しやすいため、水やりは非常に重要な管理作業になります。
土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。特に夏場は、水切れさせると生育が著しく悪くなるため、朝夕2回の水やりが必要になることもあります。
追肥は、植え付けの2週間後からスタートし、その後は月に2回程度のペースで行います。株の様子を見ながら、固形の化成肥料を株元から少し離れた場所にぱらぱらとまくか、週に1回、水やりを兼ねて規定倍率に薄めた液体肥料を与えるのも効果的です。
プランターにはミニセロリもおすすめ
プランター栽培では、「ミニホワイト」やスープセロリ(キンサイ)などのミニ品種もおすすめです。
通常のセロリよりもコンパクトに育つため管理がしやすく、クセも少ないためサラダなどに使いやすいというメリットがあります。栽培期間も比較的短いので、初心者の方でも挑戦しやすいでしょう。
露地でのセロリ栽培を成功させるには

露地栽培(畑での栽培)では、広々としたスペースで根を深く広く張らせることができるため、株を大きくがっしりと育てられるのが最大の魅力です。
成功の鍵は、植え付け前の入念な土作りと、水はけを考慮した適切な畝(うね)立てにあります。
最も重要な土作りと連作障害対策
前述の通り、セロリは酸性土壌が苦手です。植え付けの2週間前には苦土石灰をまいて深く耕し、酸度調整を済ませておきましょう。
1週間前には、土壌を豊かにするために完熟堆肥を1平方メートルあたり2~3kg、元肥として化成肥料(N-P-K=8-8-8など)を100gほど施し、土とよく混ぜ込みます。堆肥をたっぷり入れることで、土の団粒構造が発達し、保水性と排水性のバランスが良い、植物の生育に適した土壌になります。
また、セロリはセリ科の野菜です。同じ場所でセリ科の野菜(ニンジン、パセリ、ミツバなど)を連続して栽培すると、土壌中の特定の養分が欠乏したり、病原菌が増えたりして生育が悪くなる「連作障害」が発生しやすくなります。少なくとも2~3年はセリ科の野菜を栽培していない場所を選びましょう。
畝立てと効果的なマルチング
セロリは過湿を嫌うため、水はけを良くするために畝は高さ10~15cmほどの高畝にするのがおすすめです。植え付けの際には、株間を40cm以上と十分に確保します。
株間を広くとることで、株が大きく育つスペースを確保できるだけでなく、風通しが良くなり、病気の発生を抑制する効果も期待できます。
そして、露地栽培では黒マルチシートを畝に張ることを強く推奨します。マルチングには、雑草防止や土の乾燥防止だけでなく、様々なメリットがあります。
マルチングがもたらす絶大なメリット
- 雑草防止:光を遮断し、栽培期間中の面倒な雑草取りの手間を大幅に軽減できます。
- 地温の安定:土の温度変化を緩やかにし、根へのストレスを軽減します。
- 土の乾燥・肥料流出防止:水分の蒸発や、雨による肥料の流出を防ぎます。
- 病気予防:雨による泥はねを防ぎ、土中に潜む病原菌が葉に付着するのを防ぎます。特に軟腐病などの予防に効果的です。
これらの準備を丁寧に行うことが、その後の生育をスムーズにし、健康で大きな株を育て、結果的に収穫量を増やすための重要な土台となります。
最高のセロリ収穫時期を迎える育て方のコツ

- 収穫量アップにつながるわき芽の処理
- 栽培で遮光して白く柔らかくする
- セロリの収穫方法は主に2種類
- セロリの冬越しはできるのか
- 植えっぱなしで栽培する際の注意点
収穫量アップにつながるわき芽の処理

セロリの株を太く、お店で売られているような立派な姿に育てるために、絶対に欠かせない作業が「わき芽かき」です。この地味な作業を丁寧に行うか否かで、収穫できるセロリの質と量が大きく変わってきます。
植え付けから1ヶ月ほど経ち、株が順調に成長してくると、主茎の根元から小さな芽(わき芽)がたくさん生えてきます。
これは植物が子孫を増やそうとする自然な生理現象ですが、食用部分である主茎を太らせるためには、このわき芽を放置してはいけません。そのままにしておくと、本来主茎に行くべき養分がわき芽に分散してしまい、主茎が細く貧弱になってしまいます。
そのため、わき芽が小さいうちに見つけ次第、指でつまんで根元から丁寧にかき取ってしまいましょう。同時に、黄色く枯れてきた下葉や、傷んだ葉も取り除きます。古い葉を残しておくと、株元の風通しが悪くなり、多湿の状態を招いて病気や害虫の温床になるためです。
わき芽かき・下葉かきの実践ポイント
- タイミング:植え付け1ヶ月後くらいからスタートし、収穫が終わるまで定期的に(2週間に1回程度)観察して行います。
- 方法:わき芽はハサミを使わず、指でつまんでポキッと折るようにかき取ります。ハサミを使うとウイルス病などを媒介する可能性があるためです。
- 天候:作業は、株の切り口がすぐに乾いて病原菌の侵入を防げるよう、必ず晴れた日の午前中に行うのがベストです。
このひと手間をかけることで、栄養が主茎に集中し、シャキシャキとした食感が魅力の、肉厚で立派なセロリに育ちます。かき取った若いわき芽は、香りが良いのでスープの香りづけなどに利用することもできます。
栽培で遮光して白く柔らかくする

スーパーなどで市販されているセロリの茎は白くて柔らかいですが、家庭菜園で普通に育てると、光合成によって葉緑素が作られ、緑色でやや硬い茎になります。
あの白くて柔らかい、マイルドな風味のセロリにするためのプロの技が「軟白(なんぱく)処理」です。
軟白処理とは、収穫前に意図的に茎の部分に日光が当たらないように遮光する作業を指します。日光を遮ることで、葉緑素の生成が抑制され、茎が白化します。
これにより、セロリ特有の強い香りが和らぎ、食感も柔らかくなって格段に食べやすくなるのです。
軟白処理の具体的な方法とタイミング
処理を行うタイミングは、収穫を予定している3~4週間前が目安です。草丈が30cmくらいに成長した頃が始めどきです。
やり方は非常にシンプルで、株元の茎の部分を、厚手の新聞紙や段ボール紙でくるりと巻き、茎を傷つけない程度に紐で軽く縛っておくだけです。この時、葉の部分は光合成ができるように、必ず外に出しておきましょう。
少し面倒に感じるかもしれませんが、この一手間で味が劇的に変わります!セロリの独特な香りが苦手なご家族がいても、軟白処理をすれば美味しく食べてもらえるかもしれませんよ。
栄養価についての注意点
ただし、軟白処理をすると、緑色のセロリに比べてβ-カロテンなどのビタミン類の含有量は減少する傾向にあります。
例えば、文部科学省の日本食品標準成分表によると、緑色種と中間色種では成分に違いがあるとされています。栄養を最大限に摂りたい場合は緑色のまま、食べやすさを重視するなら軟白処理、というように、ご自身の目的に合わせて選んでみてください。
セロリの収穫方法は主に2種類

愛情を込めて育てたセロリ。
いよいよ収穫の時を迎えますが、収穫方法には大きく分けて2つのやり方があります。一度にたくさん使うか、それとも少しずつ長く楽しみたいかなど、ご自身の消費ペースや用途に合わせて最適な収穫方法を選びましょう。
① 株ごと収穫
スーパーで売られているような、株を丸ごと収穫する方法です。草丈が40~50cm程度に育ち、株元が十分に太くなったら収穫の適期です。
株全体を束ねるように持ち、ナイフや包丁で地面すれすれのところから一気に切り取ります。この方法は、一度にまとまった量を収穫できるので、ポトフやシチューなどの煮込み料理、ピクルス作りなどで大量に消費する場合に向いています。
② かきとり収穫
家庭菜園で特におすすめなのが、この「かきとり収穫」です。外側の十分に成長した葉柄(茎)から、その日に使う分だけを1本ずつかき取って収穫する方法です。
株の中心にある若い葉は成長点なので、ここを残しておくことで、株は次々と新しい葉を出し、長期間にわたって収穫を楽しむことができます。
| 収穫方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 株ごと収穫 | ・一度にまとまった量を収穫できる ・見た目が立派 | ・一度に消費する必要がある ・収穫時期の見極めが重要 |
| かきとり収穫 | ・必要な分だけ収穫でき無駄がない ・長期間収穫を楽しめる ・いつでも新鮮なものが味わえる | ・一度に大量には収穫できない |
収穫遅れは厳禁!「す入り」に注意
どちらの方法で収穫する場合でも、収穫が遅れすぎると茎の内部に空洞ができる「す入り」という生理障害が発生します。
すが入ると、食感がスカスカになり、味が著しく落ちてしまいます。特に株ごと収穫の場合は、大きくなるのを待ちすぎず、適期を逃さないように注意深く観察しましょう。
セロリの冬越しはできるのか

セロリは比較的寒さに強い野菜なので、霜が強く降りない関東以西の温暖な地域であれば、対策をすれば冬越しすることも可能です。しかし、そこには「とう立ち」という大きなリスクが伴います。
セロリは本来、秋に種をまいて冬の寒さを経験し、春に暖かくなると花を咲かせる二年草の性質を持っています。植物が冬の低温に一定期間さらされることで花芽が作られるこの現象を「春化(しゅんか、バーナリゼーション)」と呼びます。
冬越ししたセロリは、春になって気温が15℃以上の日が続くと、子孫を残すために花芽をつけ、花茎を伸ばす「とう立ち」を起こします。
とう立ちが始まってしまうと、株の栄養がすべて花を咲かせる方に集中してしまうため、肝心の茎は硬く筋っぽくなり、食用には適さなくなります。
そのため、野菜として美味しく食べるためには、とう立ちさせずに収穫するのが基本です。
冬越しのリスクと対策
冬越しに挑戦する場合は、強い霜に直接当たると株が傷んで枯れてしまうため、不織布をトンネル状にかけたり、プランターであれば軒下に移動させたりするなどの霜よけ対策が必須です。
とう立ちのリスクを十分に理解した上で、春先に薹が立つ前の若い茎を少し収穫することを目指すか、あるいは秋から冬の間に美味しい時期に収穫しきるかを判断しましょう。基本的には、家庭菜園では無理に冬越しさせず、旬の時期に収穫しきるのがおすすめです。
植えっぱなしで栽培する際の注意点

かきとり収穫をしながら長期間栽培を楽しむ、いわゆる「植えっぱなし」の状態にする場合、株を健康に保ち、収穫を続けるために特に注意すべき点が2つあります。
それは、「継続的な追肥」と「徹底した病害虫対策」です。
肥料切れさせないための継続的な追肥
セロリは「肥料食い」の野菜と言われるほど、その長い生育期間を通じて多くの肥料を必要とします。植えっぱなしで収穫を続けると、土の中の養分はどんどん吸収されていきます。
肥料が切れると、とたんに生育が鈍くなり、茎も細く硬くなってしまうため、月に1~2回の追肥を忘れずに行いましょう。特に、かきとり収穫で葉柄を数本収穫した後に、お礼肥として化成肥料や液体肥料を与えると、次の葉の生育が促されて効果的です。
病害虫の早期発見と管理
畑に長く置いておくということは、それだけ病気や害虫に遭遇するリスクも高まるということです。家庭菜園で特に注意したい代表的な病害虫は以下の通りです。
セロリの主な病害虫
- 軟腐病(なんぷびょう):細菌による病気。株元が溶けるように腐り、悪臭を放つ。多湿条件で発生しやすく、一度発病すると治療は困難。水はけを良くし、泥はねを防ぐことが予防の鍵。
- アブラムシ類:新芽や葉の裏に群生し、汁を吸う。ウイルス病を媒介することもあるため、見つけ次第、粘着テープで取り除くか、食品由来のスプレーなどで駆除する。
- キアゲハの幼虫:セリ科の植物を好み、食欲旺盛で、放置すると葉を食べ尽くされることもある。特徴的な見た目をしているので、見つけ次第捕殺する。
これらの病害虫を防ぐ基本は、株元の風通しを良くするために枯れた下葉をこまめに取り除くことです。日々の観察を怠らず、早期発見・早期対策を心がけてください。
また、同じ場所でセリ科の野菜を連続して栽培すると「連作障害」が出やすくなるため、一度セロリを栽培した場所では、2~3年はセリ科以外の野菜(トマト、ナス、マメ科など)を育てるように計画しましょう。
最適なセロリの収穫時期を見極めよう

この記事で解説した、セロリの収穫と栽培を成功させるための重要なポイントを、最後にリスト形式でまとめます。これらの要点を押さえて、美味しいセロリの収穫を目指しましょう。
- セロリの一般的な収穫時期の目安は秋から初冬にかけて
- 草丈が40cmから50cmに達し、株元が十分に太った頃が収穫のサイン
- 収穫が遅れると茎に空洞ができる「す入り」状態になるので注意
- 栽培初心者の方は、育苗の手間が省ける市販の苗から始めるのが安心
- 種まきは発芽適温(15~20℃)を保てる春か初夏の時期が基本
- 発芽には光が必要な「好光性種子」なので覆土はごく薄く
- 酸性土壌を嫌うため、植え付け2週間前までに石灰で土壌を中和する
- 生育期が夏と重なる場合は、遮光や敷きわらで高温と乾燥への対策を徹底する
- プランターで育てる場合は、根がしっかり張れる深型のものを選ぶ
- 土の表面が乾いたらたっぷり水を与えるのが基本、特に夏場は水切れに注意
- 生育期間が長いので、月に1~2回の定期的な追肥を忘れずに行う
- 主茎を太く育てるため、株元から出るわき芽はこまめにかき取る
- 収穫3~4週間前に遮光する「軟白処理」で、茎が白く柔らかくマイルドな風味になる
- 収穫は一度に採る「株ごと収穫」と、長く楽しむ「かきとり収穫」がある
- 温暖地なら冬越しも可能だが、春になると「とう立ち」して硬くなるリスクを考慮する